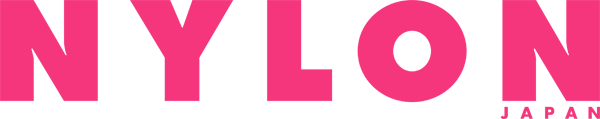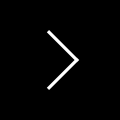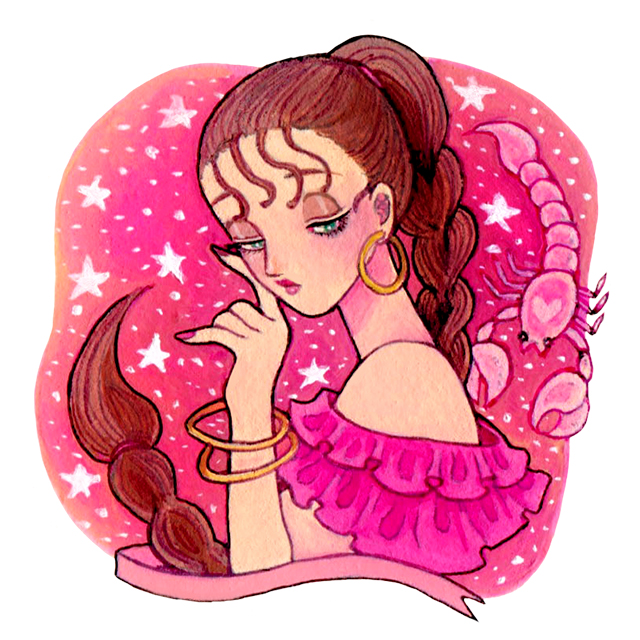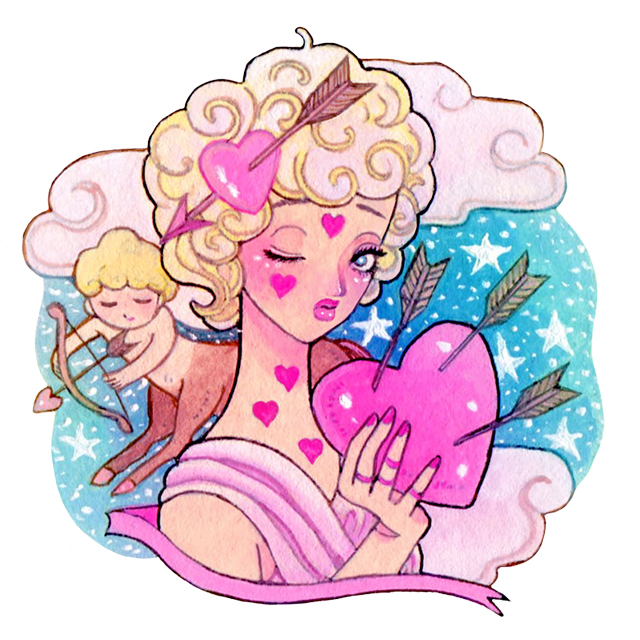CULTURE
2019.09.19
It's Work Time vol.5 manga artist Akane Torikai 鳥飼茜
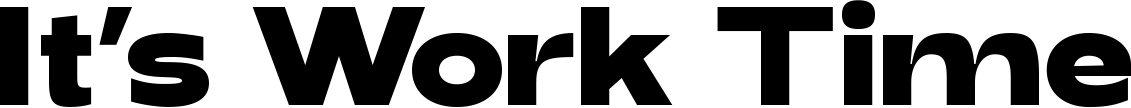

(c)鳥飼茜/小学館 週刊ビッグコミックスピリッツ連載中
夢を追い続ける全ての人へ発信するお仕事連載

憧れの仕事の極意に迫るインタビュー連載。
今回は、漫画家として数々の話題作を世に送り出してきた鳥飼茜を取材。
独特な切り口でリアルな日常を描く彼女ならではの考え方に迫った。
アシスタントを経ていちばん
得たものはプロとしての意識
-昔から絵を描くことは好きでしたか?
京都市立芸術大学に通っていたので絵はやりたかったんだと思います。でも京都には他にも私立の美大が結構あって、もっとイカしてるというか、設備もいいし、新しいことを教えてくれるところに行きたかったんですが、親を説得するのがダルくて(笑)。高いお金を出してまで、その芸大を卒業した後のリターンがあるのかどうか当時親を説得できるほど熱量がなかったし、親からの許しが出るのは公立大学しかなかったんですよね。それに、その時々によってやりたいことが変わるので親からの不信感が強くて。どちらかというと美術系の大学に通う自分=おしゃれみたいに思っていた節もありました。実際、つい7年前くらいまで「心配だから何か資格を取りなさい」ってずっと言われていたんですよ。「今からでも介護士とか取得できる資格あるんじゃないの?」って。きっと“資格”というガツンとした証拠みたいなものを見せてほしかったのかもしれないですね。
-漫画家という職業は芸大に通っている時に目指そうと思ったんですか?
そうですね、アートみたいなことをしている人の端くれでいたかったんです。もともとすごいかっこつけなんですよ。だからもし雑誌の編集を目指してたら間違いなくNYLONを受けていると思います。
-“かっこつけ”というと?
“かっこいい”ものが好きなんです。軽い気持ちで芸大に行っちゃったんですけど、芸大の人達って真面目な人が多いんですよ。一晩中絵を描いている人だったり自らコンテストに応募したり、自分でお金を払ってギャラリーを借りたり、そういう人達がたくさんいましたね。私はそこまでしたいと思えなかった。斜めに構えているように聞こえますが、自分には彼らよりもいいものができると思えなかったんです。単にやる気の熱量が彼らと全然違ったので。私のスタンスは「なんかおしゃれでいたいから」みたいなチャラい感じ(笑)。でもその人達って夜中に裸になって教室の床に自分の人拓を取ったりするようなタイプの人達なんですよ。
-大学時代はずっとそのような心持ちでしたか?
代々変わった人が多い大学なので、奇抜であるほど“神”、みたい感じで(笑)。だから自分はそこまで奇人じゃないっていうことがコンプレックスなんですよ、今も。大学の時にその気持ちが高まっていって、仕事して食べていけないって思ったのかな。芸術の世界だったら名が知られている大学ですが、一般大学に比べたら学歴も何も持っていなかったから、そのなかで無理なくお金が手に入る仕事って考えた時に子供の時に好きだった漫画がいちばん自分に合っているんじゃないかって一瞬思ったんです。アートはエンタメではないので、本当に自己表現欲求がないと成り立たないんです。漫画っていうのはその点いい感じなんですよね。メッセージ性や話の構造的なこと考えたり、画風だったり自分で自由に采配できる部分が大きいし、それが売れたらお金になる。人が面白がらなければお金にならないという仕組みがすごく確立されているじゃないですか。それに、日本だと漫画の市場って大きいですよね。対して、美術の評価って本当にわからないんですよ。一部のお金持ちや力のある人が「いいね」って評価したらその作品に100万とか多額の値がついたり。執拗に犬の毛だけをアップで描いた絵が市長賞を取ったり、圧倒されるのはわかるんだけど私には全然わからないです(笑)。そういう理屈の通じない世界だから、自分にはお手上げだなと思って。漫画のほうが結果がわかりやすいし、ダメだったらどこか就職しようと思って、普通の大学生が3年生で就職活動する感覚で漫画をイチからひとつ話を描き始めました。
-芸大とはいえ大学生だとその時期は就職先が決まる人達も多かったと思いますが、焦りを感じませんでしたか?
自分のなかでは割と順調なほうだと思っていました。今考えたらすごいなと思いますけど、1発目に描いた作品が割といい賞を取ったんですよね。といっても賞金15万円くらい。その後に出したやつは全部、少女漫画の賞金1万円の賞とか。中学生や高校生が出してもらうような賞とかと並んでるわけですよ。自分は芸大で絵を習って、年齢も上で、いろんな物事を少しは知っているつもりなのに、いざ出したらそこと同じくらいっていう感じも結構キツかった。でも、まだ若かったし、アートで食べるよりはまだ道がありそうって思っていて、運が良かったのは編集についてくれていた人が「何らかであなたは漫画家になれると思う」って言ってくれたことですね。「この雑誌じゃなくても、こういう路線じゃなくても、今はわからないけど素質はある」って言ってくれて、その言葉を単純に信じていました。でも、めげそうになったのは大学を出た後にしばらくこういう状態が続いていたので、「これ、ちょっとやっていけないかも」と思った時は焦ったこともありました。他に就職活動をしていなかったので。
-デビューするまで気持ちを持ちこたえられた理由はなんだったんですか?
その時、京都の寺町通りというおしゃれな通りのビーズ屋さんでバイトをしてたんです。自分で作ったアクセサリーも売っていたので、「こういうのもいいな」って思っていて。そのお店って女性社員と私だけだったんですよ。バイトだけど受注、発注などのお店の仕事内容が全部こなせるくらい働いていたから、正社員にならないかって声をかけられたことがあって。ゆくゆくはこのお店乗っ取れるんじゃないかって思っていたのであまり心配していなかったんだと思います(笑)。漫画の道がダメだったらこういう道でもいいなって。なんとなく京都のこういうおしゃれでこぢんまりしたお店で、自分の好きなものを作って、店舗拡張してカフェを始めたりとか、それなりにその場にいたら楽しいことはあるだろうと思っていました。だから、あともうちょっと無理だったら辞めようと思っていた時に、以前出していた作品でデビューが決まりましたっていう知らせがあったので、“ちょうど良く”という感じに近いかもしれないですね。
-鳥飼さんの“デビュー”はどのタイミングですか?
初めて読み切り作品が少女漫画誌に掲載された2004年です。
-デビューした直後いかがでしたか?
まずいちばん最初に投稿した雑誌が『モーニング』で、そこでは作風的に少女漫画のほうがいいんじゃないかと言われ、その時たまたま『別冊フレンド』という雑誌を勧められたので「もうどこでもいいです」って感じで連れて行ってもらったんです。ただ少女漫画なので、やっぱりかっこいい子と、可愛い子と、恋愛と、夢と、希望と……。そういうものが描けなきゃいけないんだろうなって勝手にすごい重圧みたいなものを感じていて。それがどうしても自分にはできないと思い込んでいたので、結構キツかったです。一応毎月のようにコンペがあったので、読み切りを描いてコンペに出して、それが通れば載せてもらえるというのが少女漫画雑誌。読者の反応が良かったりすると、上手くいけば連載をもらえたり。私の場合1、2年目はずっとただ読み切りを出すだけでした。運良くコンペには大体受かるというか、掲載はされるので誌面には載れるけど、“たくさんいるなかの1人”っていうことをずっと続けるしかなくて、本にもならないから描き捨てという感じがしていたんですよね。それが納得いかなくて、自分のなかで漫画ってこういうものだよね、こういう感じでいいのかな、って葛藤しながら描いていたからそれも嫌になってしまったんだと思います。この時代と並行して、アシスタントに就かせていただいた作家さんが少女漫画の先生ではなくて、青年誌『ヤングマガジン』の古谷実さん。私自身すごく大好きだった作家さんで、本当に今も神のような存在なんです(笑)。
-アシスタントはどのくらい経験しましたか?
1年半くらいしていましたが、アシスタントは別にしなくてすむならそれにこしたことないんです。漫画家のアシスタントというのは、まず漫画家として1回デビューが決まったとしても、すぐに仕事があるわけでは全くなくて。長いか短いかは頑張り次第でもありますが、自分の連載で食べていけるようになるまではお金もないし、でも一般的なバイトをする時間は割けない、そういう時に作家さんのところへアシスタントに行くんです。そうすると勉強にもなるし、お金ももらえるし、っていう漫画家の仕組みがあるんですけど。
-それは漫画家でないとわからない仕組みですね。
漫画は描いたら基本的に漫画雑誌の賞に作品を出すんです。昔はWEB漫画がなかったので、雑誌の編集者に持っていって読んでもらい「これだったら◯◯賞くらいだったらいけるのでは?」という流れになったんですよね。担当編集がついて次の作品を描いて、送って、でもそれは引っかからなかったり、というやり取りを1年半くらい続けました。結局大学を出た年にこれ以上やっても無理だったら何か違うことをしなきゃって思っていた時に、「デビューが決まりました」という報告があったのでギリギリのタイミングでしたね。
-古谷さんのアシスタントに就いてみて心境の変化はありましたか?
アシスタントに行くことが決まった時は、好きすぎて本当にどうにかなりそうなくらいでした。緊張しすぎて嘘みたいにずっとお腹が痛かったです(笑)。本当に古谷さんを崇めていたので職場に行くととにかく具合が悪くなるんですよ(笑)。絶対にちゃんとやらなきゃとは思うんですけど上手く描けないし、最初は全然でした。アシスタントに行く前は自分の作品を描くにもちょっと線からはみ出たり、この顔ちょっと変だなって思いながらもさっさと終わらせたいから仕上げて。新人の漫画家なんてそんなものです。私なんて特に雑な人間で、描き終わったらそれがベストって思っていて、直すのも嫌だし、かといって改善するという考えもなかったので。でも古谷さんのアシスタントをしているということは、私が描いたものの一部が古谷実さんっていうすごい人の漫画になるわけだから、ものすごく緊張しました。はみ出たら消さなきゃいけないし、ちゃんとまっすぐの線を引かないといけないし。こう言うと当たり前のことなんですけど、でもそれが最初はできなくて。勝手に「ちょっとこの子どうしよう」っていう周囲の空気もビンビンに察知していました(笑)。最初それが原因でお腹が痛くなったりして(笑)。しかも初日、先生に対して「具合が悪いので今日は途中で帰るかもしれませんがよろしくお願いします」って直接言っていたらしいんですよ。それで古谷さんは「とんでもねえのが来たな」って思ったらしくて。自分としては真面目だったからこその発言だったんですが、逆に破天荒な人って思われてしまって。今でもその扱いなんです。遅刻も1回くらいしかしたことなかったんですが、行かなきゃいけない時間に起きてしまって「これで今日クビになるかもしれないからちゃんとしておかなきゃ」って思って、ちゃんと髪巻いて準備していったんです。そしたらそれも破天荒エピソードにされて、今となっては笑い話ですが、その時は自分の一生懸命さが伝わらないなと思っていました。
-アシスタントを経験して得たものや刺激を受けたことはありましたか?
すごく刺激もありましたね、アシスタント仲間に今漫画家として活躍している人もいたので。たまにですが、今でも当時のアシスタント達と先生を交えてご飯食べに行ったりもしているんです。今となっては先生もざっくばらんに漫画の話をしてくれるようになりましたが、当時は本当に憧れの存在だったので、まさかお酒を一緒に飲めるようになるとは。今考えればすごいところまで来たなって自分でも思います。正直、アシスタントの時は自分が何の役に立っているのかわかりませんでした。でも、アシスタントとしてある程度お金をもらっていたし、自分が描いたものが先生の作品になるので、とにかく家に帰って線の練習をしたりしていましたね。いちばん印象的なのは、先生は描いている原稿をすごく直すんですよね。週刊連載で、最後時間がなくなってきた時、背景を描き終わったコマにバッテンが書いてあって、そうするともう1回描いた背景を手直さないといけない。でもそれは背景が気に入らないのではなく、先生がそこに描かれたキャラクターの絵が気に入らないから。そういう作業が結構あって。その時は正直仕事が増えるので「別にこっちでも良くない?」って思っていました(笑)。でも自分の絵に対してここまで上手くできているのに、さらに上を目指している、線がはみ出ていてもほっとくとかのレベルではないんです。そういう“プロとは”ということはアシスタントに入っていちばん得たものかな。当時「こういう少女漫画描いてます」って何回か見せた時に、「鳥飼さんは普段喋っていることのほうが全然面白いから、もっと普段喋っていることを描きなよ」と毎回言ってくれて、当時はその意味が理解できませんでしたが、今は自分が思っていることをだいぶ描けるようになりました。
-ではデビューしてからについてお聞きします。根本的な話になりますが、具体的に漫画家の仕事がどういうものなのかを教えてください。
漫画、どうやって作っているんでしょうね(笑)。最初は本当にわからなかったです。「私漫画家で」と言うと多くの人に「自分も小学生の時になりたかったんですよ!」と言われるんです。「小学生の頃からずっと描いていたの?」とよく聞かれますが、たぶんみなさんと同じくらいだと思います。漫画の扉絵だけをマネして描いて終わり、みたいな感じなんですよね。それは私も同じで、大学の時に最初に漫画を描いた時は本当に何を描いたらいいのかわからない、どういうものを物語と呼ぶのかわかりませんでした。絵を描いたことはあるけど、物語を考えたことがなかったからどうやって考えるんだろうって。当時、段々と漫画のなかに文学っぽいというか、やまだないとさんや、南Q太さんみたいな方々が描いていらしたような本当にただ日常の一瞬を切り取っただけっていう漫画がすごくイケてるって思ったんです。恋人とも友達ともつかない男が家に出入りしている、というような。それだけでも「うわ、かっこいい」って思って、物語に起承転結がなかったとしても情感やリアルさで見せられる、みたいなものをやってみたかったんです。今でも物語を作るのは苦手。その時から自分のやり方として使っているのは漫画のなかでどの顔を見せたいか、ということ。読み切りでも連載でも出てくるこの女の子のこういう時に振り返った瞬間の顔とか。顔だけじゃなくても、立ち姿でも一緒ですが、(NYLON JAPAN 8月号のカバーストーリーを見ながら)吉沢亮さんのこの表情が欲しい、みたいことがあるじゃないですか。女性モデルだと特にあると思いますが、意思のある写真ってすごくいいですよね。そのピークの顔になるまでの前後に物語を付け加えているという感じ。だから前後の話は別にどうでもいい(笑)。そこの顔にどうつなげるか、余韻を残せるかっていうための物語なんです。それがデビュー当時からずっと私がやっているやり方です。
次のページ : 仕事のなかでいちばん好きなのは...

|
Akane Torikai/鳥飼茜 1981年生まれ、大阪府出身。2004年に読み切りデビュー。2010年には『おはようおかえり』が青年誌に初掲載され、2014年に「このマンガがすごい!2014」にてオンナ編第9位。2015年「第39回講談社漫画賞」一般部門にて『おんなのいえ』がノミネート。月刊モーニングtwoにて2013年10月号〜2017年11月号まで連載していた代表作『先生の白い嘘』は、「このマンガを読め! 2015」で第8位。現在、週刊ビックコミックスピリッツにて『サターンリターン』が隔週連載中、第1巻発売中。
Twitter
Instagram |
ILLUSTRATION: AKANE TORIKAI
INTERVIEW: KAHO FUKUDA
DESIGN: SHOKO FUJIMOTO
WEB DESIGN: AZUSA TSUBOTA
CODING: NATSUKI DOZAKI