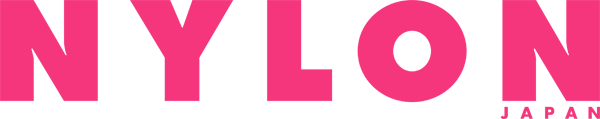オダギリ ジョーは、キミに問う
一言だけでは到底言い表せない、異彩な魅力を放つ俳優オダギリ ジョー。
9月公開の長編映画『ある船頭の話』を完成させ、
映画監督としての才能を確実なものとした。
その背景には僕達には想像もつかない道のりと、彼ならではの想いがある。
現代を生きる人に投げかける問いかけと共に、
大人の男の持つ多面的な魅力を感じ取ってほしい。

邪悪ささえ、人の光。
毎日船を渡すその川に、まもなく大きな橋が架かるー。オダギリジョー監督による長編映画『ある船頭の話』は、
船頭として生きながら時代の移ろいに翻弄される「トイチ」を中心に描かれる。
美しく静かな映像のなかに垣間見える狂気と、変わりゆく人々の姿は、
オダギリが突きつける「人はどうあるべきか」という問いかけそのもの。
現代に生きる私達は、狂気と希望を携えて、
どうやって生きていけばいいのだろうか?
『ある船頭の話』は、船頭のトイチを中心に展開していきます。船頭という仕事に注目したきっかけをまずは教えてください。
10年くらい前に、テレビで見たのがきっかけです。熊本に球磨川という川が流れていて、小さな舟を渡している船頭の方(八郎さん)がいたんですよ。それを見て「綺麗だな」という思いと、「この職業がいつか消えていくことがもったいない」という思いを抱きました。職業も文化も、時代と共に消えてゆくものってたくさんある。失ってしまって良いのかな、どうなのかな? と考えているうちに、その船頭の方に直接話が聞きたくなって、実際に会いに行ったんです。
現代にも、船頭という職業があるんですね。
そうなんです。本当にわずかな人数しか残っていないんですよ。2週間くらい生活を共にして、自分でカメラを回してインタビューしたり、船頭がどんな生活をしているのか、ずっと撮らせてもらったんです。八郎さんと話すうちに、今の社会の仕組みのなかにあった違和感とリンクして、それでこのストーリーに結びついていきました。
主人公のトイチは仕事に真摯に向き合っていますよね。船を渡しながら人と人との関わりが生まれる様子が印象的でした。
トイチにとっては、それが生きるということなんですよね。球磨川の八郎さんは1日にせいぜい1人か2人のお客さんを渡すだけなんです。いつ来るかわからないお客さんを待ち続けている。でも、自分が船を動かして役に立っていることが幸せで、そこで生まれる会話が楽しみだ、とピュアに話してくれました。そんな船頭の日常を細かく描くことでしか、トイチという人物の生活は描けない、と思いましたね。トイチは、川に橋が架かることで、自分はもはや必要とされなくなるんじゃないか、という不安も抱えています。その葛藤を中心軸にして描く、というところから着想しました。
オダギリさん自身が、「失われていってしまう」と感じた出来事はありますか?
ありとあらゆるものが失われていきますよね。例えば雑誌とかテレビの状況も大きく変わりつつある。映画だって同じです。携帯電話が生まれて、家の固定電話も公衆電話もなくなった。スマートフォンで文字を打つから、漢字を書けない人が増えている。新しい何かが生まれると、何かが失われていく。それがいいのか悪いのかは僕が決めることではないし、それぞれが判断すればいいと思うんですけど、世の中どうなっていくんだろうという漠然とした不安は常にありますね。
俳優として、変化する時代の先端にいるなかで、そういった感覚が生まれたのでしょうか?
僕は時代の先端にいるというイメージは全くなくて、むしろその逆にいようと思っています。多くの人が良いと思うものが本当にいいものか、わからない。ものの価値が数によって決まってしまうのは危ないですよ。「流行」の方にはなるべく行かないように、一貫して自分のやりたいことだけを心掛けています。

top¥42,000 t-shirt\17,000 by julius
pants\146,000 by yohji yamamoto
shoes stylist's own
現代社会はテクノロジーの側に傾いていて、変化のサイクルも速くなっているように感じます。オダギリさんは、人のあるべき姿はどのようなものだとお考えですか?
僕個人は自然の側に立ちたいけれど、テクノロジーを否定するつもりはないですね。世の中って、いろんなことが許されていいはずなんです。便利で無駄のない生活を追い続ける人にとって、それが幸せならそれでいい。自分はそういう便利さよりも、人間的な生活の方が豊かに感じる性質というだけで。
人間的な生活、豊かさとは、どういったものなのか、という話にもつながりますね。
この作品で、その大きな問いを投げかけてみました。「これが正解だ」と決めつける必要はなくて、個人が好きなようにとらえて、自分にとって何が豊かなのかを掴みとればいいのかなと思っています。
今作は変化の過程を丁寧に描いていて、登場人物の変わり方も印象的でした。オダギリさんが自分に近い存在として感じる人物はいましたか?
自分と近いかどうかはわかりませんが、理想は永瀬正敏さんが演じた仁平です。彼はマタギ(東北地方の山間に住む猟師)なんですけど、この作品のなかで唯一、最初から最後まで変わらないんです。橋ができることで様々な人生の角度が変わりゆくなかで、自分の価値観や生活が変わらないのは仁平だけ。自分にとって何か大切なのか、わかっているからなんでしょうね。
変わってしまう人々の姿を眺めながら、「仕事」って、人が尊厳を持って生きていく上で重要な鍵なのかもしれない、と感じました。
たしかに……そうですね。なんて言ったらいいのかな。一方で僕自身は、仕事を絶対的なものだとは捉えていないんです。現代は生きていく上でお金が必要で、そのために働くという選択肢が一般的。でも、資本主義的な、お金が中心に回る世の中が正しいかと言うと、そうじゃないという思いもある。複雑ですよね。僕の勝手な価値観で言わせてもらうと、働かなくても生きていけるのであれば、それでいいとも思う。自給自足の生活だって選択肢のひとつです。人それぞれいろいろな事情があるから、勝手なことは言えないけれど、僕は絶対的に仕事が必要だとは考えていないんですよ。それなのに、仕事を通して尊厳を獲得するという物語を描いたのだと思うとちょっと不思議ですね。
誰かに必要とされたり、他人と関わり続ける装置としての「仕事」の必要性を感じました。それは、自分自身の生活のなかでも感じてきたことだったので、そのように受け止めたのかもしれません。監督の意図を超えて、登場人物がそれぞれ人格を持っているということで、物語自体が生き始めるということなのかな、と。
それが映画の面白いところですよね。受け取る人の状況や考え方によって、様々な解釈が生まれる。だから、映画はわかりやすい答えを提示すべきではないと思います。物語が生き始めた、と感じていただけたのは、作り手としてはすごくうれしいですし、それだけでこの映画を作った価値があると思いますね。