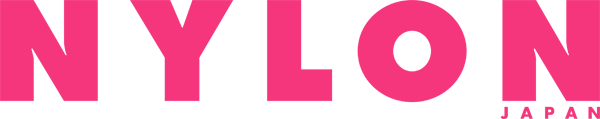オダギリさんが、映画というものに対して持っている思いを教えていただきたいです。
映画がいろんなことを教えてくれたんですよ。こんな世界もあって、世の中にはこんなことが起こっていて、こういう人達がいて……。ファッションも音楽も文化も、かっこよさを教えてくれたのも映画でした。自分にとって絶大な影響を与えてくれたものなんです。エンターテインメントとしての映画も、それはそれでひとつの映画の役割だと思うけれど、僕はアートやカルチャーとして映画を捉えています。
エンターテインメントの映画と、アート・カルチャーとしての映画の差はどういうところにあると思いますか?
冒頭の話とも関係するんですけど、大衆を意識するかしないかというのは大きいと思います。大衆を楽しませる要素を、計算して入れるのがエンタメ。「絶対に泣ける」というようなことですね。それはそれで、すごく難しいことだとも思います。一方で、アートとしての映画には作り手の強い意志やメッセージが必要なのだと僕は考えています。
受け手が想像力を持つということがどんどん減っていて、時代の変化のなかで「わかりやすいもの」や「バズるもの」に注目が集まるような構造になっていますよね。
最近そういったことをよく耳にしますね。僕としては人間の感性や想像力というものは、いつまでも信じていたい。この映画を作った理由のひとつも、そういったところだと思います。この映画の大きな挑戦のひとつです。
ラストシーン、すごく印象的でした。どう判断していいかわからない、終わりとも捉えられないような。
確かに、彼らの人生はあのあとも続きますからね。人によってはハッピーにも、アンハッピーにも見えると思いますが、どう捉えられてもその人の好きなように解釈してもらえればと思います。

top¥70,000 by yohji yamamoto
実は、この映画を試写会で観たあと、こんな映画を観たよって知人に話しながら涙が出たんです。反芻しながらいろいろ思い出して感情に届きました。
え、ほんとですか(笑)。それはうれしいな。「泣かそう」なんて全く思ってなかったので、そういう感想はちょっとびっくりするんです。引っかかる人にとって引っかかる作品であるというのはすごくうれしいし、一本の映画で人生が変わることもあるじゃないですか。「あの映画を観たから自分の人生が変わった」っていう、この映画が誰かのそういう作品になったら本当にうれしいですね。
「売るために映画を作る」のではなく、純粋にやりたいこと、描きたいものを作るという意志があったように感じます。
やっぱり自分にしか作れないものを作らないと、何かを作る意味ってないじゃないですか。自分だったら何ができるかっていうのを突き詰めないと意味がないと思うんですよ。だから売れる売れないとかを考えることよりも、何ができるか、何を作るべきかということの方が僕にとっては重要性が高いというか。それで売れないのはしょうがないじゃないですか、売れるに越したことはないですけど(笑)。
その考え方はオダギリさんの考える、人としてこうありたいという考えに関わってくるのかな、と。
職人のように何か1つのことに打ち込める人ってものすごく素敵じゃないですか。真面目に物事に向かって、それを長期間続けられる人って、やっぱりすごいと思うんですよ。そういう人はかっこいいし、やりたいことを明確に持っている人というのが理想なんじゃないかなって気はしますね。ちょっとしたことで揺らぐのは、やっぱりかっこ悪い。それが自分を持っているということなのかな。平凡な言い方になってしまいますけれど。
オダギリさんは、俳優業から監督業へ重心を置き換えるということを考えられているんですか?
いえ、全然。何かを描きたいという衝動がないと映画って作れないので、これからそういうものがあればまた作るでしょうし、「作ってほしい」とか「作らなきゃいけない」とかっていう状況で作るのはおかしな話だと思いますね。自分で作りたいという思いが、今後どのタイミングなるかは今はわからないですね。
俳優業と監督業の考え方の違いは、大きいですか?
そんなこともないですよ。俳優としてもやりたくない仕事はするべきじゃないと思うし、興味が持てないのに仕事を受けるっていうのは失礼だと思う。やっぱり僕は、俳優としてもこだわりが強いほうだとは思いますね。
話が戻るのですが、映画のなかで印象的だったのがトイチの中にある邪悪さです。自分の邪悪さをどう飼い慣らしていくか、って、それも人間の大きなテーマですよね。オダギリさん自身のなかにもそういう思いはありますか?
人間って、良い面も悪い面もある。1歩間違えれば犯罪を犯したのかもしれないし、善くありたいと思いながらも、どこかで悪い自分が出てきたりもする。でもそれを否定することもないと思うんですね。それが人間だからこそ、認めてあげたいんです。そういう視点に立ってこそ、「本当の人間」が見えるんじゃないかなと思います。僕のなかにも狂気はもちろんあって、それを野放しにするのではなく、いかにコントロールするか、ということは考えます。そういう自分が船頭という静かな存在を描くうえで、抑えられない衝動があったのは確かですね。静かな作品を静かに描くだけでは満足できなかった。自分の悪いところも含めてわき上がったものでした。人間を描くうえでも避けられないものだったと思います。
殺人事件が起きた時に、加害者について想像することは決して多くないですよね。人生のどこかのタイミングがずれていたら、もしかしたら犯罪を犯していたかもしれない、という想像力も時には必要なのかなと。
幸いなことに、俳優って自分のなかにある狂気を利用できるんですよ。作品のなかでそれを表現に昇華させられるから、僕はなんとかやってこれたんだなと思うんです。物を作る人は、それぞれ、そういう狂気と向き合って乗り越えているんだと思うんです。

オダギリさんの人生のターニングポイントはいつでしたか?
アメリカに留学したことはターニングポイントですね。日本の美術のクラスで、課題と違うものを作ったら×になるじゃないですか。アメリカでアートのクラスを取った時に、英語がよくわかってなくて、絵を描く課題に対して立体造形を作っていっちゃったんです。でも先生が逆に褒めてくれて。「これはお前の個性だ。」みたいなこと言ってくれて、すごい国だなと。アートっていうのはなんでも受け止められる自由さ、懐の深さがある。日本にいる時は気づかなかったことでしたね。
15周年のナイロンのテーマは、『NEW POWER NO BORDER』なのですが、オダギリさんの思想や人生は、そういったテーマを体現しているように思います。
何かにボーダーがあるとかないとかってこと自体を考えたことがなくて、僕は俳優として海外の作品に携わる時にも、「海外作品だからやる」みたいな思いはないんです。たまたま海外の作品の台本が面白かったから、とか、その時時間があったから、やってるだけなんです。「ハリウッドに行きたい」っていう俳優さんもいるけれど、海外にばかり目が行って、自分の足もとがちゃんと見えてないと成功はしないですよね。自分の目の前にあるものと誠実に向き合う。今置かれた状況でどんな事ができるのか? やり残していることはないか? どんな自由があるか。それができていないならば、どこに行っても難しいですよね。まずは自分の手の届く範囲のことを考えて、100%やるべきなのかなと思いますね。自分を信じれば、結果はあとからついてきます。
最後に、NYLONの読者にメッセージを。
突き詰めるべきですよ、何が好きで、何に影響されてるかをどんどん深めていくことがスタートだと思います。最初はあやふやなものでも、それを突き詰めていくと自分が見えてきて、そこから自分が発信できるようになってくる。ファッションにしても、自分の方向性を狭めていくなかでスタイルができると思う。なんか、偉そうですかね。すみません(笑)。
オダギリ ジョー/おだぎり・じょー
1976年2月16日生まれ、岡山県出身。2003年第56回カンヌ国際映画祭に出品された黒沢清監督の映画『アカルイミライ』で初主演。その後、日本アカデミー賞、ブルーリボン賞をはじめ国内外の数々の賞を受賞。2019年も数多くの作品に出演する予定で、秋には『時効警察』の新シリーズ『時効警察はじめました』が12年振りに復活。映画監督としても複数の作品を手掛ける。
『ある船頭の話』
オダギリ ジョー長編初監督作品『ある船頭の話』が、2019年9月13日(金)から新宿武蔵野館ほか全国ロードショー。主演・柄本明をはじめ豪華キャスト・スタッフが集結して描く、人間の根源を見つめる物語。
STAFF
MODEL:JOE ODAGIRI(DONGYU)
INTERVIEW: TAIYO NAGASHIMA
PHOTOGRAPHY:TOSHIO OHNO
STYLING:TETSUYA NISHIMURA
HAIR&MAEKUP:YOSHIMI SUNAHARA(UMITOS)
EDIT:SHOKO YAMAMOTO
DESIGN:SHOKO FUJIMOTO
CODING: JUN OKUZAWA